Sceneお試し会のメンバーはなかなかタフな要求を出してくれます。
「ねえ皆さん、次回のお試し会テーマに何か希望ありますか?」
「"練り切り"を勉強してみたい!」
「勉強って、作り方を学びたいの? 」
「そうそう、色の出し方とか分からなくて!」
「うわ〜、ここでお菓子を作ってみると言うことだよね。 難題を投掛けてくれるねえ、一応検討はしてみるけど・・・」
で、先日和菓子の顧問をお願いしています巌邑堂の内田さんを訪ねて相談に乗って頂きました。
すると、なんと!私たちの依頼を受けて下さるとおっしゃるのです。
お試し会々場で勉強会(“練り切り”作り体験教室)が実現することになりました。
次回お試し会は、開始9年目にして初めての試み"練り切り作り体験教室"を開催することになりました。巌邑堂の内田さんありがとうございます。
【巌邑堂代表取締役 内田弘守さん】
ところで、"練り切り"ってどんなものか皆さん詳しくご存知ですか?
私は『お茶会の席での"お茶請け"の代表格』くらいしか知らないので少々調べてみました。

練り切りは、白餡に求肥(ぎゅうひ:蒸すかゆでた白玉粉や餅米の粉に、砂糖や水飴を加えて練ったもの)やツクネイモを混ぜて練った生菓子。
適度なやわらかさと粘度があり、これを様々な形を彫刻した木型に押し付けたり、手やへらで整形して細工を施し、食紅やクチナシなどの食用色素で彩色して、和菓子に仕上げる。 そのまま和菓子に仕上げられる他、他の材料とも組み合わされ餅菓子などにもなり、季節に合わせた様々な色・形の物が作られる。








【“練り切り”参考画像】(サムネイル)
序に「練り切り」という言葉の語源が気になり調べてみました。
『餡を炊くことを「練る」と言い、大きな銅の鍋で絶えず木べらで練り続けながら加熱する。簡単に終わるものでは無く、決して分離する事の無い状態に迄練り上げる。で、最後まで完全に練り切ると言うことから“練り切り”と呼ばれるようになった。』
と言うことだそうです。


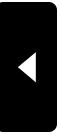

この記事へのコメント :