
お盆の季節ですね。
お盆には旧盆(8月13日~16日)と新盆(7月13日~16日)があって、多くの地方では旧盆を祝いますが。
遠州地方では新盆で祝う所が多いようで、特徴として”遠州大念仏”があります。
当ブログのフォロアーさんの中には県外から移住された方も少なからず居られるでしょう。
そんな皆さんもご存知かとは思いますが、表題の『遠州大念仏』に触れてみます。
“遠州大念仏”、私の知る範囲で解説してみます。
「遠州大念仏」は遠州地方特有の郷土芸能で、初盆の家から依頼されると、家の庭先で大念仏を演じます。 大念仏の団体は、必ず家の手前で隊列を組み、統率責任者の提灯を先頭にして、笛・太鼓・鉦(かね)の音に合わせて行進します。笛・太鼓・鉦・歌い手、そのほかもろもろの役を含めると大きな団体は30人を越えます。 大念仏の一行が初盆の庭先に入ると、太鼓を中心に両側に双盤(そうばん)を置いて、音頭取りに合せて念仏やうたまくらを唱和します。そして、太鼓を勇ましく踊るようにして打ち鳴らし、初盆の家の供養を行います。

入場から退場までに要する時間は30分ほどです。 江戸時代のもっとも盛んな時期は、約280の村々で大念仏が行われていました。 現在は45組程が遠州大念仏保存会に所属し、その殆どが旧浜北市域にあります。 また、現在も犀ヶ崖では、毎年7月15日に三方原合戦の死者の供養として、遠州大念仏が演じられています。
何故この話題に触れようと思ったか⁉️

昨日“あまの”で呑んだ帰り道、遠くからの懐かしい音に惹かれて近づくと、子ども達が遠州大念仏の練習をしていました。

上島は、遠州大念仏保存会の最南端に位置して、後輩への伝承育成に力を入れています。
私事ですみませんが・・・、
実は僕も幼少期の一時期、子ども連に入って遠州大念仏を練習していました。
父親が亡くなった翌年の初盆で、我が家でも遠州大念仏を演じてもらったことを懐かしく思い出します。


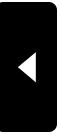

コメント