“ランナーズ・ハイ”と言う言葉がある。
ちょっと調べてみた。
『マラソンやジョギングを行うと通常、次第に苦しさが増してくるが、それを我慢し走り続けるとある時点から逆に快感・恍惚感が生じることがある。この状態をランナーズ・ハイと呼ぶ。多くの検証実験から、この状態においては脳内にα波とモルヒネ同様の効果があるβ-エンドルフィンという快感ホルモンに満たされていることが判明した。この内、β-エンドルフィンの増大が麻薬作用と同様の効果を人体にもたらすことで起こるとされる。運動中にβ-エンドルフィンがどう働くかのメカニズムは解明されていない。
今までは上記のような解説であった。ところが、これが覆されることになった。
2015年頃からの研究により、ランナーズハイをもたらせる物質はβ-エンドルフィンではなく、体内で生成される脳内麻薬の一種である内在性カンナビノイドに属する化学物質であるとする説が提示された。内在性カンナビノイドは、マリファナに含まれるTHCと同様に不安を和らげたり、痛みを感じにくくさせる性質がある。
2015年のネズミを使った実験では、ホイールに乗せられ走らされたネズミにアナンダミドと呼ばれる内在性カンナビノイドが生成されたことが確認された。そのネズミを熱したプレートに乗せストレスに対する反応を観察した結果、ネズミの血中アナンダミドは増加し、熱さに反応するまでに通常より時間がかかった。さらにアナンダミドの受容体をブロックした実験では、長距離を走っていないネズミ同様に、熱いプレートに早く反応する結果となった。一方、β-エンドルフィンの受容体をブロックしたところ、熱いプレートに対する反応には全く変化は見られず、このことからこれまで考えられてきたβ-エンドルフィン説は覆り、内在性カンナビノイドがランナーズハイの原因物質であるとされた。』
“クライマーズ・ハイ”と言う言葉がある。
登山家が極度の興奮状態に陥った末、危機感覚を麻痺させてしまうことを言う。
これもまた脳内麻薬・内在性カンナビノイドが影響していると言われる。
では、『ドライバーズ・ハイ』 ってあるのだろうか?
以下、私の体験談である。
私は自分のことを無類の“ドライブ好き”と思っている。
娘たち二人が大学生だった8年間(4年✕2)、京都へ往復500kmの距離を毎月のように車で通っていた。
同僚たちから「500キロを毎月って、小倉おかしくないか!」と失笑された。
が、私はこの距離と運転が全く苦にならなかったし、むしろ楽しみでもあった。
今でもハンドルを握ると気持ちが落着き高揚する自分がいる。
よくドライブフリーク仲間(SDFF)たちと長距離ドライブの話題で盛り上がる。
(以前(今年3月)当ブログにアップした記事 ⇒ https://sceneblog.hamazo.tv/e8760484.html)
で、私の夢であり目標でもあった(1,500km/1日)ドライブが昨日実現した。
“24時間以内に1,500km走る”、未体験ゾーン突入に少々興奮していた所為だろう。
前日23時にベッドに入り就寝して目が覚めたのは2時間後の1:00AM。
1:30AMに出発して戻ったのは当日の7:30PM。
18時間掛けて走行した距離は1,547km❗️
 ⇐
⇐ 
勿論私の新記録であり、SDFF仲間のトップ記録にもなった。
単純計算で、コンスタントに時速100kmで走っても15時間掛かる距離である。
1〜2時間毎のトイレ休憩と食事休憩併せて2時間見積もり17時間ほどを想定していたのでほぼ予定通りであった。
ただ、睡眠2時間の後に17時間ぶっ通しの運転は疲労感と睡魔が襲ってこないか不安だった。
ところが、運転中疲労感もなく睡魔も全く襲ってこなかった。
むしろ快感のようなある種の興奮状態が終始己を支配していたような気がする。
運転していた間私の脳内で何が起きていたのかは定かではない。
ただ、この感覚は何かが覚醒して私の脳を制御していた、そんな気すらする。
そう、もしかしたらこれが“ドライバーズ・ハイ”状態なのかも知れない。




さて、1,500kmをどんな所(ルート)走行したのか・・・、
FB友達は私の昨日のタイムラインをトレースして大凡推測されているだろう。
ドライブフリークな皆さん、運転を語り合おう。


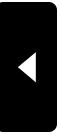

コメント