12月に入って俄かに珈琲豆の焙煎量が増えてきた。
で、Sceneにおける珈琲豆の年間焙煎量を月別に調べてみた。
結果12月が圧倒的に多く年間焙煎量の約2割を焙煎しているが、これには理由がある。
Sceneに限らず全国的に珈琲の消費量は冬季に増える傾向にあり、特に12月は多くなる。
加えて、Sceneでは常顧客の珈琲豆仲間の皆さんに向けて“冬季珈琲豆感謝セール“を実施する。
そのため12月に集中焙煎作業が発生するので一気に数値が上がる。
(本音を記すと、週休3日にさせて頂いたことで集中焙煎が大変楽になった❣)
珈琲消費量に関連して色々調べていたところ政府(総務省)の資料の中に非常に興味深いデータを見つけたので記すことにした。
【総務省の家計調査からコーヒー消費量の都道府県別ランキング】
家計調査は全国から10000世帯を抽出して調査して、二人以上の世帯の購入量を比較している。一般世帯における購入量と消費量はほぼ同じと考えて、ここでは消費量としている。
家計調査には県庁所在地と政令指定都市の数値が掲載されており、複数の調査都市がある県はそれぞれの値を人口比で按分した数値を、それ以外の県は県庁所在地の数値を県の消費量としている。また、年による変動が考えられるので2014年~2018年の平均値をとっている。

コーヒー消費量の全国平均は2,432.2gで1日あたり6.66g。家計調査ではインスタントコーヒーとコーヒー豆を一括してコーヒーとしているが、仮にこれをインスタントコーヒーとすると、コーヒーカップ約3.3杯分になる(一杯2gとして計算)。
消費量が最も多いのは京都府で3,567.0g(偏差値78.9)。こちらは1日あたり9.77gで約4.9杯分だ。
2位は広島県で3,238.2g。3位以下は鳥取県(3,196.4g)、滋賀県(3,083.4g)、奈良県(3,007.4g)の順。一方、最も消費量が少ないのは静岡県で1,816.2g(偏差値28.9)。これに熊本県(1,947.8g)、鹿児島県(1,967.2g)、宮崎県(2,008.6g)、福井県(2,098.2g)と続いている。
喫茶費用がダントツだった岐阜県と愛知県の消費量はそれほど多くなく、両県は家よりも喫茶店で飲むことが多いからだ。
相関ランキングではマーガリン、ジャム、パン、牛乳の消費量と正の相関があり、これらはセットで消費量が多い。パン食文化が盛んなところでコーヒーの消費量も多いと言える。
順位 都道府県 消費量 偏差値
1 京都府 3,567.0g 78.92
2 広島県 3,238.2g 69.53
3 鳥取県 3,196.4g 68.34
4 滋賀県 3,083.4g 65.11
5 奈良県 3,007.4g 62.94
6 石川県 2,991.2g 62.48
7 島根県 2,949.8g 61.30
8 北海道 2,860.4g 58.75
9 富山県 2,859.6g 58.72
10 岡山県 2,766.0g 56.05
11 青森県 2,744.4g 55.43
12 福岡県 2,741.4g 55.35
13 山口県 2,727.8g 54.96
14 香川県 2,725.0g 54.88
15 神奈川県 2,690.0g 53.88
16 岩手県 2,687.0g 53.80
17 愛媛県 2,678.2g 53.54
18 千葉県 2,671.2g 53.34
19 徳島県 2,667.8g 53.25
20 埼玉県 2,601.6g 51.36
21 新潟県 2,590.6g 51.04
22 茨城県 2,585.0g 50.88
23 山形県 2,560.4g 50.18
24 愛知県 2,556.2g 50.06
25 大分県 2,492.0g 48.23
26 大阪府 2,480.0g 47.88
27 東京都 2,467.4g 47.52
28 高知県 2,447.2g 46.95
29 岐阜県 2,413.6g 45.99
30 和歌山県 2,396.0g 45.49
31 三重県 2,389.6g 45.30
32 宮城県 2,383.2g 45.12
33 栃木県 2,379.2g 45.01
34 兵庫県 2,372.0g 44.80
35 群馬県 2,354.0g 44.29
36 長崎県 2,321.8g 43.37
37 沖縄県 2,313.6g 43.13
38 佐賀県 2,309.4g 43.01
39 秋田県 2,286.0g 42.34
40 福島県 2,245.2g 41.18
41 長野県 2,205.4g 40.04
42 山梨県 2,202.8g 39.97
43 福井県 2,098.2g 36.98
44 宮崎県 2,008.6g 34.42
45 鹿児島県 1,967.2g 33.24
46 熊本県 1,947.8g 32.69
47 静岡県 1,816.2g 28.93
全国 2,432.2g
静岡県人は珈琲消費量が少ないことは分かってはいたが、まさかまさかの最下位である❗️
日本のほぼ中央に位置して県境を挟み隣接する愛知県と静岡県の結果は対極と言えるほどの違いがある。
何ゆえこれほどの差異が生じるのだろうか?
で、調べたくなったのが緑茶の消費量・・・、
【総務省の家計調査から緑茶消費量の都道府県別ランキング】
家計調査は全国から10000世帯を抽出して調査して、二人以上の世帯の購入量を比較している。一般世帯における購入量と消費量はほぼ同じと考えて、ここでは消費量としている。
家計調査には県庁所在地と政令指定都市の数値が掲載されており、複数の調査都市がある県はそれぞれの値を人口比で按分した数値を、それ以外の県は県庁所在地の数値を県の消費量としている。また、年による変動が考えられるので2014年~2018年の平均値をとっている。

1世帯あたり緑茶消費量の全国平均は986グラム。最も消費量が多いのは茶所静岡県で1,901グラム。これは全国平均の2倍近い消費量だ。2位以下は奈良県、京都府、福井県、長崎県と続いている。奈良や京都が上位に入っており、日本文化と緑茶は関係があるようだ。
1位の静岡県と2位の京都府はともに多くのお茶を消費しているところだが、両者の購入費用には大きな違いがある。静岡県の緑茶購入費が10,899円なのに対し、京都府は5,192円と静岡の半分以下。100gあたりの単価にしてみると静岡県が573円で京都府は311円。金額が高くてもこだわりのお茶を楽しむのが静岡なら、関西人らしく経済的にお茶を楽しむのが京都と言うことだろうか。
分布地図を見ると本州中央部で消費量が多く本州の両端で消費量が少ない同心円上の分布となっている。
相関ランキングでは炭酸飲料消費量と負の相関があり、お茶の消費量が多いところは炭酸飲料の消費量が少ない。イメージ的にもお茶と炭酸飲料は対極のようだが、消費量でも対照的となっている。
順位 都道府県 消費量 偏差値
1 静岡県 1,520.8g 80.70
2 三重県 1,349.4g 72.83
3 鹿児島県 1,229.0g 67.30
4 滋賀県 1,189.4g 65.48
5 奈良県 1,119.6g 62.28
6 京都府 1,104.4g 61.58
7 長崎県 1,098.0g 61.29
8 佐賀県 1,050.0g 59.08
9 和歌山県 1,030.8g 58.20
10 石川県 1,024.6g 57.91
11 千葉県 1,000.0g 56.78
12 福岡県 944.6g 54.24
13 秋田県 935.8g 53.84
14 熊本県 919.4g 53.08
15 福井県 917.8g 53.01
16 神奈川県 916.7g 52.96
17 愛知県 892.4g 51.84
18 埼玉県 888.0g 51.64
19 東京都 871.4g 50.88
20 茨城県 864.4g 50.56
21 大分県 857.2g 50.23
22 島根県 849.8g 49.89
23 岐阜県 845.6g 49.69
24 宮崎県 841.6g 49.51
25 宮城県 838.6g 49.37
26 新潟県 826.0g 48.79
27 長野県 823.2g 48.67
28 大阪府 816.4g 48.35
29 群馬県 803.4g 47.76
30 栃木県 803.2g 47.75
31 富山県 791.4g 47.21
32 広島県 781.6g 46.76
33 山梨県 767.8g 46.12
34 兵庫県 709.0g 43.42
35 山口県 708.4g 43.39
36 岩手県 694.0g 42.73
37 福島県 678.2g 42.01
38 高知県 667.0g 41.49
39 愛媛県 620.8g 39.37
40 北海道 616.4g 39.17
41 香川県 613.4g 39.03
42 山形県 597.6g 38.31
43 徳島県 586.6g 37.80
44 岡山県 584.0g 37.68
45 青森県 551.4g 36.18
46 鳥取県 462.6g 32.11
47 沖縄県 454.0g 31.71
全国 846.4g
私が推測した通りである。
静岡県は緑茶の国ゆえ、お茶を愛飲する量が多くなり、自ずと珈琲の消費量は減る。
隣接する愛知県と静岡県、その珈琲(喫茶店)文化の大きなギャップに納得である。
歴史に培われた“緑茶王国静岡県“、そこに珈琲文化が割り込むのは至難の技のようだ。








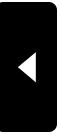

コメント