美術館情報2弾め❕
豊橋市美術博物館で明日(2月22日)から始まる美術展のご案内です。

「異端」「鬼才」「風雲児」—さまざまな呼び名を与えられた中村正義(豊橋出身 1924-1977)。 日展画家として前途を嘱望されながら、会員に推挙された1961年に師中村岳陵のもとを離れ、日展を脱退した正義は、以後旧態依然とした体制の日本画壇に反逆し、「日本画」の概念をくつがえすような表現を行い戦後の日本美術の流れの中でも特異な存在とみなされてきました。とはいえ、その活動は孤絶したものではなく、同時代の作家たちと深くつながり、台風の目のように周囲を巻き込んで美術界に波乱を巻き起こし、美術作家を取り巻く社会の在り方について問題提起をつづけます。 生誕100年を記念する本展は、代表作による画業の概観はもちろんのこと、そうした交友関係にも着目し、関連する作家たちの作品もあわせて紹介することで、周囲との関係性の中にあらためて正義を見出すものです。また、映画や舞台美術、住宅や写楽研究など正義の関わった多様な活動にも焦点をあて、約180点の作品と資料から正義の実像に迫ります。

第Ⅰ章「研鑽の時代―日展と蒼野社」
中村岳陵の画塾〈蒼野社〉に入門して早々、日展に入選したのは正義22歳の時。以後、2度にわたって特選を獲得し、画壇の注目を集めた。1946年以降の研鑽期から日展特選作家となるまでの展開を代表作で追うとともに、師岳陵や兄弟子たちの同時期の作品を紹介し、若き日の正義を育んだ画塾〈蒼野社〉の社風をみる。
第Ⅱ章「反逆の兆し―日展復帰と一采社」
快進撃を続けた正義も病には勝てず、4年間の療養生活を送る。1958年の復帰後に発表された一連の日展委嘱作品には、それまでとは異なる正義の方向性と戦略、画家として個性を確立しようとする意志が垣間見える。そうした正義の変化と実験性に影響を及ぼした髙山辰雄や山本丘人など、〈一采社〉に関わる作家たちの作品も合わせて展観する。
第Ⅲ章「日本画壇への挑戦―日本画研究会発足」
1961年に日展を脱退した正義は、以後「日本画」の概念をくつがえすような色彩と表現、手法で画壇を挑発。一方で在野画家たちとのつながりを求め、針生一郎らに呼びかけて〈日本画研究会〉を発足した。この時期の大胆不敵な正義の表現に加え、研究会の片岡球子や横山操・加山又三をはじめ、正義が導いた地元の在野画家たちの個性が会場で競い合う。
第Ⅳ章「生と死の狭間で―人人会と東京展」
星野眞吾・山下菊二らと美術グループ〈人人会〉を結成し、活動を開始した正義。その会場問題が端緒となって〈東京展〉市民運動へと展開する。事務局長として奔走する一方、大腸がん手術と闘病生活を余儀なくされ、作品はしだいに死の影を深めていく。〈人人会〉の同志や〈東京展〉に力を添えた井上長三郎・岡本太郎らの作品とともに凄絶な晩期の作品をみる。
第Ⅴ章「深掘り!中村正義をよみ解く」
代表作の展観では語りきれない、正義の多様な側面と取り組みを紹介!
1「自画像から顔へ―自己への凝視」

2「風景と山水―写生から心象風景へ」

3「花と女―色彩の実験」

4「多面的活動―挿絵・ポートレイト・舞台・建築・浮世絵研究」

5「祈りの造形―仏画・水墨人物・書」

地元豊橋市出身の奇才中村正義の生誕100年を記念しての催事。
豊橋市美術博物館ではかなり力を入れて紹介しています。
日展を脱退し、「反骨・奔走の偉材」「異端の天才画家」「日本画壇の風雲児」と呼ばれて独自を道を切り拓いた中村正義。
絵画、特に日本画に興味ある方はこの機会に訪ねて鬼才中村正義のことを知るのは如何でしょう。
豊橋市美術博物館で明日(2月22日)から始まる美術展のご案内です。

「異端」「鬼才」「風雲児」—さまざまな呼び名を与えられた中村正義(豊橋出身 1924-1977)。 日展画家として前途を嘱望されながら、会員に推挙された1961年に師中村岳陵のもとを離れ、日展を脱退した正義は、以後旧態依然とした体制の日本画壇に反逆し、「日本画」の概念をくつがえすような表現を行い戦後の日本美術の流れの中でも特異な存在とみなされてきました。とはいえ、その活動は孤絶したものではなく、同時代の作家たちと深くつながり、台風の目のように周囲を巻き込んで美術界に波乱を巻き起こし、美術作家を取り巻く社会の在り方について問題提起をつづけます。 生誕100年を記念する本展は、代表作による画業の概観はもちろんのこと、そうした交友関係にも着目し、関連する作家たちの作品もあわせて紹介することで、周囲との関係性の中にあらためて正義を見出すものです。また、映画や舞台美術、住宅や写楽研究など正義の関わった多様な活動にも焦点をあて、約180点の作品と資料から正義の実像に迫ります。

第Ⅰ章「研鑽の時代―日展と蒼野社」
中村岳陵の画塾〈蒼野社〉に入門して早々、日展に入選したのは正義22歳の時。以後、2度にわたって特選を獲得し、画壇の注目を集めた。1946年以降の研鑽期から日展特選作家となるまでの展開を代表作で追うとともに、師岳陵や兄弟子たちの同時期の作品を紹介し、若き日の正義を育んだ画塾〈蒼野社〉の社風をみる。
第Ⅱ章「反逆の兆し―日展復帰と一采社」
快進撃を続けた正義も病には勝てず、4年間の療養生活を送る。1958年の復帰後に発表された一連の日展委嘱作品には、それまでとは異なる正義の方向性と戦略、画家として個性を確立しようとする意志が垣間見える。そうした正義の変化と実験性に影響を及ぼした髙山辰雄や山本丘人など、〈一采社〉に関わる作家たちの作品も合わせて展観する。
第Ⅲ章「日本画壇への挑戦―日本画研究会発足」
1961年に日展を脱退した正義は、以後「日本画」の概念をくつがえすような色彩と表現、手法で画壇を挑発。一方で在野画家たちとのつながりを求め、針生一郎らに呼びかけて〈日本画研究会〉を発足した。この時期の大胆不敵な正義の表現に加え、研究会の片岡球子や横山操・加山又三をはじめ、正義が導いた地元の在野画家たちの個性が会場で競い合う。
第Ⅳ章「生と死の狭間で―人人会と東京展」
星野眞吾・山下菊二らと美術グループ〈人人会〉を結成し、活動を開始した正義。その会場問題が端緒となって〈東京展〉市民運動へと展開する。事務局長として奔走する一方、大腸がん手術と闘病生活を余儀なくされ、作品はしだいに死の影を深めていく。〈人人会〉の同志や〈東京展〉に力を添えた井上長三郎・岡本太郎らの作品とともに凄絶な晩期の作品をみる。
第Ⅴ章「深掘り!中村正義をよみ解く」
代表作の展観では語りきれない、正義の多様な側面と取り組みを紹介!
1「自画像から顔へ―自己への凝視」

2「風景と山水―写生から心象風景へ」

3「花と女―色彩の実験」

4「多面的活動―挿絵・ポートレイト・舞台・建築・浮世絵研究」

5「祈りの造形―仏画・水墨人物・書」

地元豊橋市出身の奇才中村正義の生誕100年を記念しての催事。
豊橋市美術博物館ではかなり力を入れて紹介しています。
日展を脱退し、「反骨・奔走の偉材」「異端の天才画家」「日本画壇の風雲児」と呼ばれて独自を道を切り拓いた中村正義。
絵画、特に日本画に興味ある方はこの機会に訪ねて鬼才中村正義のことを知るのは如何でしょう。








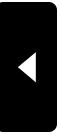

コメント